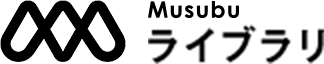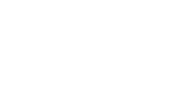この記事は 5 分で読めます
マーケティングファネルとは?顧客を取り逃がさないための分析方法を紹介

マーケティング活動を通じて集客を行っても、すべての見込み顧客が購買につながるとは限りません。反対に、僅かな購買によって爆発的な影響を市場に与えられるケースがあります。
こうした顧客の動きを予め設計して、戦略的に動かすためのフレームワークに「マーケティングファネル」というものがあります。
今回は、マーケティングファネルの基本や、BtoBにおけるファネルの活用方法などを紹介します。
目次
マーケティングファネルとは、顧客の行動を「ファネル(漏斗)」の形で表したモデルのこと
マーケティングファネルとは、数多くの見込み顧客がだんだんと購買に近づいていく様子や、購買した顧客がだんだんと市場に影響を及ぼしている様子をファネル(=漏斗)の形で表したモデルです。
図形の面積の大きさが、実際の見込み顧客の数に比例しており、下部に進むにつれて顧客数は減少していきます。

上の図が典型的なマーケティングファネルのモデルになります。広告代理店などでよく使用されるAISASという購買モデルをベースにしており、2つのファネルで構成されています。
マーケティングファネルの代表的な3種類
マーケティングファネルには、大きく分けて3つの種類があります。それぞれ着目するポイントや活用方法が異なるため、自社のビジネスモデルや目的に合ったファネルを選択することが重要です。
パーチェスファネル

パーチェスファネルは上図の上にある逆三角形のマーケティングファネルで、見込み顧客が購買に至るまでのプロセスを表しています。
今回は特に有名なAISASモデルに準拠したマーケティングファネルをご紹介します。AISASモデルは顧客の行動を「認知→興味→比較・検討→購買→拡散」という形で表しています。パーチェスファネルでは購買までの4段階を扱います。
- 認知(Attention)
消費者の注意を引くフェーズ - 興味(Interest)
消費者の興味を引くフェーズ。 - 比較・検討(Search)
製品・サービスに関心を持った消費者が自ら情報を検索し、競合との明確な比較の中で自社製品が選ばれるかどうかのフェーズ - 購買(Action)
製品・サービスを購入するフェーズ
インフルエンスファネル

インフルエンスファネルは、上図の下にある三角形のマーケティングファネルで、顧客の購入後の行動に焦点を当て、実際に購買に至った顧客が口コミやレビューなどを通じて市場に顧客を増やしていく流れが示されています。顧客との長期的な関係性を構築し、ブランドへの愛着を高めることで、アンバサダー的な存在を増やしていけます。
ダブルファネル

ダブルファネルはパーチェスファネルとインフルエンスファネルを組み合わせたモデルです。顧客の購入プロセスを「認知」から「購入」、「アドボカシー(支持者化)」まで一気通貫し、顧客満足の向上につなげることを表しています。
ダブルファネルは、以下の4つのフェーズで構成されています。
- プロモーションフェーズ
認知度を高め潜在顧客を獲得するためのフェーズ - アクイジションフェーズ
潜在顧客の意識を高めるフェーズ - リテンションフェーズ
顧客の満足度を高め、リピート購入を促進するフェーズ - インフルエンスフェーズ
顧客をブランドの支持者に育成するフェーズ
BtoBマーケティングにおけるファネルの活用方法
各フェーズに適したコンテンツ戦略を行う
BtoBにおけるファネルマーケティングでは、見込み顧客が次のフェーズに進むことを促すようなコンテンツ設計が必要です。各段階ごとに単発でコンテンツを提供するのではなく、ファネル全体を見据えたコミュニケーション設計が求められます。
パーチェスファネルの各段階に適したコンテンツ戦略には以下のようなものがあります。
- 認知段階
ブログやSNSを通じて業界情報を提供し、バナー広告やディスプレイ広告を使って目標企業にリーチする。さらに、PR活動やプレスリリースで認知を高める - 興味段階
ホワイトペーパーやウェビナーで情報提供し、直接的なコミュニケーションを図る。さらに、メルマガを通じて継続的なナーチャリングを行う - 比較・検討段階
事例集や導入実績を公開し、自社の強みや実績をアピールする。さらに、無料の製品デモを提供して顧客に体験してもらう。 - 購入段階
レビュー・口コミによって既存顧客の声を紹介し購買意欲を促進する。さらに、見積りシミュレーターを設置して価格面の不安を解消する
ファネル分析を行い予算を最適化する
ファネル分析とは、マーケティングファネルの各段階における顧客の行動を数値化し、どの段階で課題があるのかを特定する分析手法です。ファネル分析を行うことで、ファネルごとのマーケティング施策の予算配分を最適化でき、より精度の高いターゲティングを実現できます。
マーケティングファネルが古いと言われる理由は、購買行動の変化に対応しきれていないため
近年、マーケティングファネルに対して「もう古い」「時代にそぐわない」といった意見が聞かれるようになりました。その理由には、インターネットやモバイル端末の普及、SNSの発達により、消費者の購買行動が多様化・複雑化していることが挙げられます。
また、近年のビジネスモデルは、サブスクリプションやシェアリングエコノミーなど、「所有」から「利用・体験」へと変化しつつあります。このように購入後の体験や満足度が重要視される中、「購入」をゴールとするマーケティングファネルでは、購入後の消費行動を検討することはできないため、時代遅れだと言われています。
BtoBでは今でも有効なフレームワークだと考えられる
ただし、購買行動の変化に対応できないのは主にBtoCの話です。BtoBの現場では、購入プロセスが直線で、関係者も複数となる傾向が多いため、マーケティングファネルは妥当なフレームワークだと言えます。
また、BtoBの購買プロセスは、BtoCほど情緒的な要素が入るほうが少なく、比較的シンプルです。そのため、マーケティングファネルを用いて購買プロセス全体を俯瞰することが可能です。
最後に、効果的に見込み客を獲得するために、ぜひ弊社が提供する営業リスト作成ツール「Musubu」をご活用ください。 業界や企業規模、設立年月から現在求人を出している企業まで、細かなセグメントでのリスト作成が可能です。
⇒ 営業リスト作成ツール「Musubu」の詳細をみる
| 監修 | |
|---|---|
 |
Baseconnect株式会社 マーケティングチーム マネージャー 河村 和紀(かわむら かずき)大手人材紹介会社に新卒入社。その後、Webメディア「ferret」を運営する株式会社ベーシックに入社。営業、営業企画、イベントマーケを経て、マーケティングマネージャーに就任。 2022年、Baseconnect株式会社に参画。イベントを中心とした、ユーザーとのコミュニケーション領域を管轄する。 主な寄稿実績『マーケター1年目の教科書』、『MarkeZine(マーケジン) vol.66』 |