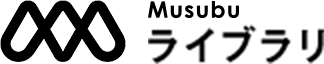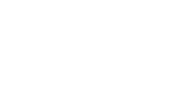この記事は 4 分で読めます
決裁者とは?|商談中に探り、聞き出すことを意識しよう

営業において、重要なのは商談を成功に導くことです。しかし、いくら熱心に商品やサービスの魅力を伝えても、最終的な意思決定権を持つ決裁者の承認が得られなければ、契約の締結には至りません。
今回は、商談成功のカギを握る決裁者について、重要性や見極め方、アプローチ方法などを詳しく解説します。
目次
決裁者とは、購買に関する最終権限を持つ人物のこと
決裁者とは、企業における購買や契約の最終決定権を持つ人物のことを指します。商談を行う際、相手方の担当者が購入を決定する権限を持っていないということは少なくありません。多くの場合、重要な決定には上位の管理職や、その他のステークホルダーの承認が必要となります。
例えば、新しいシステムの導入や大型設備の購入などの高額な支出を伴う意思決定には、通常、部長職以上の承認が求められます。また、経営方針に直結するような案件については、取締役会での決議が必要となることもあるでしょう。
決裁者の承認なしでは、いかに優れた商品やサービスであっても成約に至ることはできません。決裁者を特定し、そのニーズを把握した上で適切にアプローチを行い、決裁者の理解と納得を得ることが極めて重要だと言えます。
「承認者」「稟議」との違い
決裁者と混同されやすいものに、「承認者」や「稟議」があります。
- 承認者:決裁プロセスの途中で承認を行う人物のこと。最終的な決定権は持たない。
- 稟議:決裁を得るための正式な手続きや書類のこと。
一般的に、「承認者」による承認は決裁に至るまでの一つのステップであり、「稟議」は決裁を得るための手段です。例えば上司が「承認」をした後、より上の役職者が「決裁」を行い、企業としての判断を示します。その際の手続きが「稟議」である、というイメージです。
ただし、中には「最終承認」を決裁と同じような意味で認識している企業や、「承認」と「決裁」を同義として使用している企業もありますので注意しましょう。
決裁者の見極め方
決裁者を特定することは、商談成功のための重要なステップです。ここでは、決裁者を見極めるための効果的な方法をいくつか紹介します。
企業規模や組織構成から推測する
企業の規模や組織構成は、決裁者を見極める上で重要な手がかりとなります。一般的に、中小企業の場合は社長や経営幹部が決裁者であることが多く、大企業になるほど、各部門の責任者や専門部署が決裁者となる傾向があります。
具体的には、従業員数が50名以下の小規模企業であれば、社長自身が決裁者である可能性が高いです。一方、従業員数が1,000名を超えるような大企業の場合は、調達部門や経理部門などの専門部署が決裁権を持つことが多いでしょう。
過去の取引事例から類推する
過去に同業他社や自社で類似の商談を行った事例があれば、それを参考にすることも有効です。過去の事例から、どのような役職の人が決裁者であったかを分析し、現在の商談に活かすことができます。
例えば、同業他社が類似の商品を販売した際、営業部長が決裁者であったという情報があれば、自社の商談でも営業部長が決裁権を持つ可能性が高いと推測できます。また、自社の過去の商談で特定の役職者が決裁者であった場合、同じ役職者が決裁者である可能性が高いでしょう。
商談中の会話から探る
商談の中で、決裁者に関する情報を聞き出すことも重要なスキルです。ただし、「誰が決裁者ですか」と直接的に聞くのは失礼に当たる場合があるため、会話の流れの中で自然に情報を引き出すことが求められます。
例えば、「御社ではこのような案件の意思決定はどのようなプロセスで行われるのでしょうか」といった質問を投げかけることで、決裁者に関する情報を得ることができます。また、「前回の案件では、○○部長に最終的な判断をいただきましたが…」といった過去の事例を引き合いに出すことで、現在の決裁者を聞き出すこともできるでしょう。
商談中の会話から情報を引き出すためには、それまでに相手との信頼関係を築いておくことが重要です。真摯な態度で相手の話に耳を傾け、適切なタイミングで質問を投げかけることが求められます。
社内の人脈を活用する
自社の社内に対象企業との接点を持つ人物がいる場合は、その人脈を活用することも有効です。社内の人脈から、決裁者に関する情報を入手したり、紹介を得たりすることで、商談をスムーズに進めることができます。
例えば、過去にターゲット企業との取引経験がある営業担当者がいれば、その担当者から決裁者に関する情報を入手することができるかもしれません。また、対象企業の出身者が自社に在籍している場合は、その人物から社内の意思決定プロセスについて情報を得ることができるでしょう。
ただし、社内の人脈を活用する際は、情報の取り扱いに注意が必要です。機密情報を不適切に扱うことのないよう、社内のルールを遵守し、適切な範囲で情報を入手・活用することが求められます。
決裁者へのアプローチ方法
決裁者を特定した後は、効果的な方法でアプローチすることが重要です。ここでは、決裁者へのアプローチ方法について、具体的に説明します。
信頼関係を構築する
決裁者との信頼関係を築くことは、商談においてとても重要です。
挨拶や期日を遵守するといった基本的な事項を徹底することはもちろん、自社の商品やサービスに関する深い知識を持ち、決裁者の質問や懸念に的確に答えられるようにしておきましょう。専門知識を提供することで、決裁者からの信頼を得て、アドバイザーとしての地位の確立を目指します。
課題やニーズを把握する
決裁者へ効果的にアプローチするためには、決裁者の抱える課題やニーズを的確に把握することが重要です。決裁者の関心事や要望を理解することで、適切な提案を行うことができます。
決裁者の課題やニーズを把握するために有効なのは、直接対話する機会を設けることです。対話の中で、決裁者が現在直面している問題や達成したい目標について聞き出すことを心がけましょう。
また、相手の所属する業界や企業の動向を調査し、理解を深めておくことも重要です。業界特有の課題や競合他社の動向を把握することで、決裁者の関心事を予測し、的確なアプローチにつなげることができます。
企業の利益につながる提案を行う
決裁者の承認を得るためには、自社の商品やサービスが企業の利益にどのように貢献するかを明確に示す必要があります。そのためには、決裁者の視点に立ち、企業の目標達成や課題解決につながる提案を行うことが重要です。
提案を行う際は、自社の商品やサービスの特徴や強みを明確に伝えます。他社との差別化ポイントを強調し、導入によって得られるメリットを具体的に示すことで、決裁者からの理解を深めることができるでしょう。また、提案内容が企業の戦略や方針と合致していることも忘れずに示しましょう。
担当者に決裁権がない場合の対処法
商談を進める中で、担当者に決裁権がないことが判明した場合、どのように対処すべきでしょうか。ここでは、担当者に決裁権がない場合の効果的な対処法について説明します。
担当者を軽視せず丁寧に対応する
担当者に決裁権がないからといって、担当者を軽視してはいけません。担当者は、決裁者との橋渡し役を担っており、商談を進める上で重要な存在です。
担当者との信頼関係を損ねてしまうと、決裁者へのアプローチが難しくなるおそれがあるため、担当者にも敬意を払い丁寧に対応することが重要です。意見や懸念に耳を傾け、真摯に対応することで、良好な関係を維持しましょう。
担当者が報告しやすい情報や資料を提供する
担当者に決裁権がない場合、担当者が決裁者に商談内容を伝えやすいようにすることが重要です。担当者が決裁者に説明しやすいように、自社の商品やサービスの特徴、導入メリット、他社との差別化ポイントなどを明確に示した資料を準備しましょう。
また、担当者が決裁者の関心事や懸念事項を把握している場合は、それらに対する説明や解決策を盛り込むことも有効です。担当者が商談内容を的確に決裁者に伝えられるよう、提供する情報や資料作成に工夫をして、積極的にサポートしましょう。
担当者のメリットも加味した提案をする
担当者に決裁権がない場合でも、担当者自身にメリットのある提案を行うことで、商談を前進させることができます。
例えば、自社の商品やサービスを導入することで、担当者の業務効率が向上したり、担当者の評価が上がったりするようなメリットを提示することが考えられます。担当者にとってのメリットを明確に示すことで、担当者が商談に積極的に関与し、決裁者への報告がスムーズに進む可能性が高まります。
最後に、新規顧客獲得の際には、ぜひ弊社が提供する営業リスト作成ツール「Musubu」もご活用ください。
業界や企業規模、設立年月から現在求人を出している企業まで、細かなセグメントでのリスト作成が可能です。
⇒ 営業リスト作成ツール「Musubu」の詳細をみる
| 監修 | |
|---|---|
 |
Baseconnect株式会社 マーケティングチーム マネージャー 河村 和紀(かわむら かずき) 大手人材紹介会社に新卒入社。その後、Webメディア「ferret」を運営する株式会社ベーシックに入社。営業、営業企画、イベントマーケを経て、マーケティングマネージャーに就任。 主な寄稿実績『マーケター1年目の教科書』、『MarkeZine(マーケジン) vol.66』 |