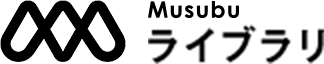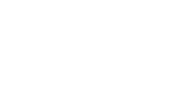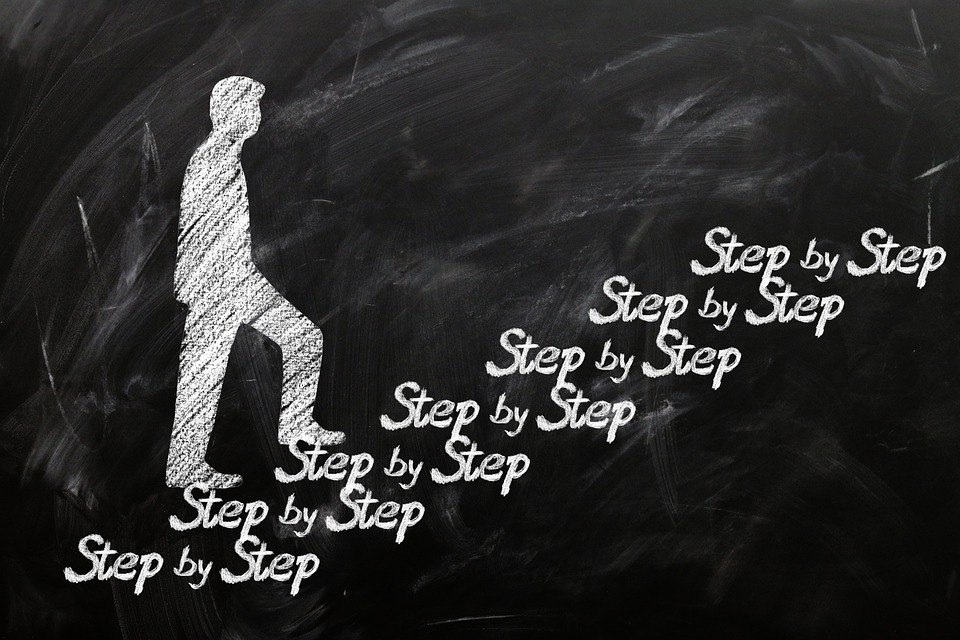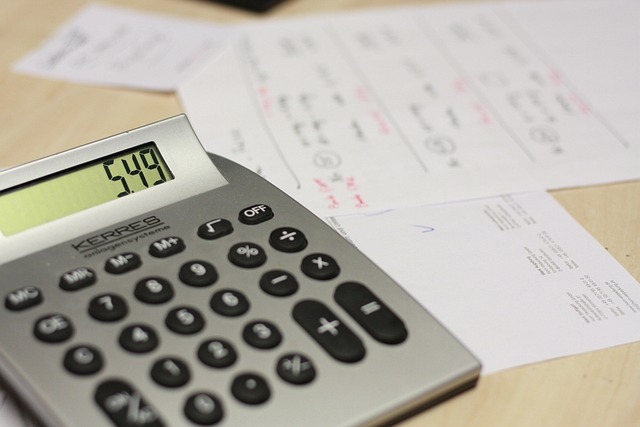262の法則をご存知ですか?聞いたことがないという方や、知っているけれど活用方法がよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、262の法則の意味や人間関係構築・マネジメントにおける活用方法、活用の際の注意点について紹介します。
目次
262の法則とは、上位層が2割、中間層が6割、下位層が2割に分かれるという法則のこと
262の法則とは、集団の人材構成は、上位層が2割、中間層が6割、下位層が2割に分かれる法則のことを指します。
262の法則を人間関係に当てはめると、「自分のことを好ましく思う人が2割、どちらでもない人が6割、嫌いな人が2割」を意味します。企業内のマネジメントに当てはめると、「有能な人が2割、普通な人が6割、成果が低い人が2割」という意味になります。262の法則を活用することによって、より良い人間関係の構築やマネジメントが可能です。
「パレートの法則」との関係
パレートの法則とは、結果の大部分(8割)の成果は全体の一部(2割)から生み出されるという法則であり、「2:8の法則」とも呼ばれます。パレートの法則は経済学者ヴィルフレド・パレート氏が提唱した法則であり、262の法則の起源となったと言われる法則です。262の法則はパレートの法則が形を変え、人間関係の構築やマネジメントに応用されたものです。
パレートの法則についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

262の法則を人間関係構築に活用する方法
嫌われることを気にしない
誰かに嫌われることを気にしない方が、気楽な人間関係を構築できます。262の法則によれば、どのような集団に属したとしても自分を嫌う人が2割は存在することになります。したがって、自分がどのように行動しても誰かには嫌われてしまうと理解した上で、嫌われることをおそれない方がより気楽な人間関係を構築できます。
環境を変えてみる
現在の人間関係に不満があるときは、思い切って環境を変えてみることも大切です。262の法則は集団ごとにそれぞれ成り立つことから、環境を変えれば自分の立ち位置も変わり、これまでよりも良好な人間関係を構築ができる可能性があります。
自分らしさを大切にする
自分らしさを大切にすることも人間関係の構築には重要です。262の法則によれば、集団内の2割の人には嫌われる一方で、他の2割には好かれることになります。自分のことを嫌う人に合わせるために自分らしさを捨ててしまうよりも、ありのままの自分を好きでいてくれる人に合わせて生きる方が気が楽でしょう。
262の法則をマネジメントに活用する方法
上位層2割には難易度の高い課題を与える
企業内の上位層2割には、より難易度の高い課題を与えるのが効果的です。上位層2割は高い能力を持っており、特別に指導しなくても成果を出すことができるため、より企業の業績に影響が出やすい難易度の高い課題を行わせるのが重要になります。
また、上位層2割にマネジメント能力の教育を行い、指導者として育成することも企業の成長には大切です。
中間層6割には目標を明確化して正当な評価を与える
中間層6割には目標を明確にして正当な評価を与え、積極性を高めることが大切です。中間層は業務に対して積極性を欠くことが多く、上位層ほど優秀とは言えませんが、上位層2割へと成長する可能性を秘めた人材がいます。積極性を高める施策を講じることで、業績の向上につながります。
下位層2割には現状や改善点を把握させて成長のサポートをする
下位層2割には、現状や改善点を把握させて成長の手助けをすることが重要です。成果が出せない原因を究明して、場合によっては業務を変更したり軌道修正のサポートを行うことによって、将来的に大きく成長する可能性があります。現時点で成果が出ないからといって、すぐに冷遇したり解雇したりしないようにしましょう。
262の法則を活用する際の注意点
人間関係構築やマネジメントにおいて262の法則を活用する際は、対象となる人物や自分がどの層に属するのかを把握した上で、適切な対応をとることが大切となります。
また、262の法則が集団に当てはまるとしても、あらゆる集団に必ず当てはまるとは言えないことにも注意が必要です。同じようなバックグラウンドや学歴を持つ集団においては、262の法則が当てはまらない場合もあると理解しておくことが重要です。




今さら聞けない、営業マネージャーが知っておくべきKPI・KGI
無料でダウンロードするために
以下のフォーム項目にご入力くださいませ。