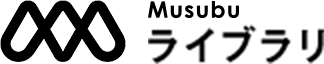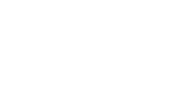マーケティング戦略を立てる時、「アプローチするべき顧客」と「するべきでない顧客」をどのように分類していますか?全てのターゲットに対して同じようにアプローチしていたら、効果が薄いだけでなく、無駄なコストもかかってしまいます。
今回は、顧客分類についての基本的な考え方から主要な分析手法、実践ポイントなどを詳しく解説します。
マーケティングにおける顧客分類の重要性
顧客分類とは、顧客を様々な基準で分類し、グループ化することを指します。これにより、企業は顧客の行動パターンや嗜好、ニーズなどを把握し、それぞれのグループに最適化した精度の高いマーケティング施策を展開することができます。顧客との関係性を可視化することで、優良顧客の維持・育成や、新規顧客の獲得に向けた戦略立案が可能となるでしょう。
さらに、優良顧客に経営資源を集中させることで、売上やLTV(顧客生涯価値)の最大化を図ることができるため、効率的な経営資源の配分が実現します。
代表的な顧客分類の基準
顧客分類を行う際には、様々な基準や方法を用いることができます。ここでは、代表的な分類基準として、「顧客との関係性」「購買行動」「属性」の3つに着目します。
顧客との関係性に基づく分類
顧客との関係性に基づく分類では、企業とのかかわり方や、ロイヤルティの度合いによって顧客をグループ化します。具体的には、「新規顧客」「リピート顧客」「優良顧客」「休眠顧客」などに分類することが一般的です。
この分類により、それぞれの顧客層に合わせたコミュニケーション戦略を立案することができます。
購買行動に基づく分類
購買行動に基づく分類では、顧客の購入頻度や金額、購入商品などをもとにグループ化を行います。例えば、「ヘビーユーザー」「ライトユーザー」、「バラエティシーカー(様々なブランドを購入しようとする層)」「ブランドロイヤル(特定のブランドを好んで購入する層)」といった分類が挙げられます。
購買行動を分析することで、顧客のニーズや嗜好をより深く理解し、効果的なプロモーションや商品開発に活かすことができます。
属性に基づく分類
属性に基づく分類では、年齢や性別、居住地域、職業、家族構成などの人口統計学的な特徴をもとに顧客をグループ化します。これにより、ターゲットとする顧客像を明確にし、最適なアプローチを行うことが可能となります。
これらの分類基準を組み合わせることで、より詳細な顧客像を捉えることができます。例えば、「20代の女性で、月に1回以上購入する優良顧客」といったように、複数の基準を用いてセグメントを細分化することで、より精度の高いマーケティング施策を展開できるでしょう。
顧客分類の5段階モデル
顧客分類の代表的なモデルとして、「顧客分類の5段階モデル」があります。このモデルでは、顧客を以下の5つのセグメントに分類します。

- 潜在顧客:自社の商品やサービスを知らない、もしくは必要性を感じていない層
- コールドリード:接点の少ない見込み顧客で、商品やサービスを認知しているが、購入には至っていない層
- ホットリード:接点の多い見込み顧客で、商品やサービスに興味を示し、購入に至る可能性が高い層
- 一般顧客:ある程度の頻度で購入する、平均的な顧客層
- 優良顧客:購入頻度が高く、高い満足度を示す顧客層
この5段階モデルを用いることで、分類された各セグメントに適したマーケティング施策を立案し、効率的な顧客獲得や育成を図ることができます。
顧客分析の主な手法
顧客分類の後は、各セグメントの特徴やニーズを深く理解するために、様々な手法を用いた顧客分析を行うことが重要です。ここでは、代表的な分析手法であるRFM分析を中心に、その他の手法についても紹介します。
RFM分析
RFM分析は、顧客の購買行動を「Recency(最終購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(購入金額)」の3つの指標で評価し、顧客をセグメント化する手法です。
RFMの各指標について、顧客を以下の基準ごとに5段階で評価します。
- R(Recency):最終購入日から現在までの期間の長さ
- F(Frequency):一定期間内の購入回数
- M(Monetary):一定期間内の総購入金額
各指標のスコアを合計し、顧客をグループ化することで、優良顧客や休眠顧客など、セグメントごとの特徴を把握することができます。これにより、セグメントに合わせたマーケティング施策の立案や、優先順位の決定が可能となります。
【RFM分析を行う際の手順】
- 分析対象期間の設定
- 顧客ごとのR、F、Mのスコア付け(5段階)
- 各指標のスコアに基づく顧客のセグメント化
- 各セグメントの特徴分析とマーケティング施策の立案
RFM分析は顧客の購買行動に着目した分析手法であり、ECサイトなど、購買データが豊富に蓄積されている事業において特に有効です。

デシル分析
デシル分析は、顧客を購入金額順に10等分し、上位から順に10%ずつグループ化する手法です。各グループの購入金額や顧客数を分析することで、上位顧客の特徴や、売上への貢献度を把握することができます。
デシル分析は、顧客の購入金額の分布を可視化し、マーケティング施策の優先順位付けに活用されます。
デシル分析の詳しい説明は、以下を参考にしてみてください。
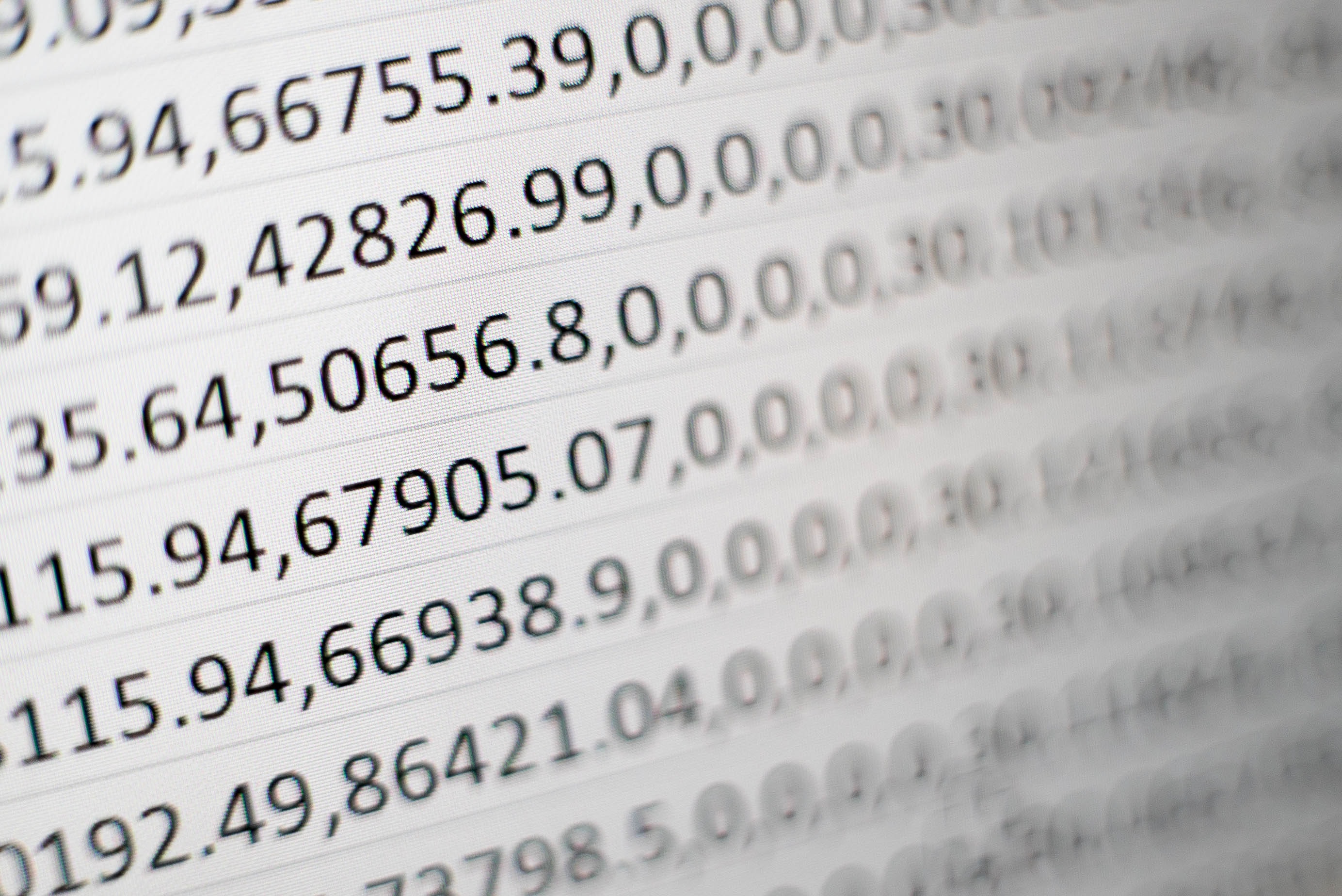
セグメンテーション分析
セグメンテーション分析は、顧客の属性や行動、ニーズなどに基づいて、同質性の高いグループに分類する手法です。年齢、性別、居住地域、ライフスタイルなどの変数を用いて、ターゲットとなる顧客像を明確にすることができます。
セグメンテーション分析は、市場を細分化し、効果的な商品開発やプロモーション活動に役立てられます。
セグメンテーションの詳しい説明は、以下の記事を参考にしてみてください。

RFMC分析とRFM-D分析
RFM分析に、顧客の購入商品カテゴリ(C:Category)や、店舗までの距離(D:Distance)を加味した分析手法も存在します。
例えば、商品カテゴリを加味したRFMC分析では、ある顧客が高額なカテゴリの商品を頻繁に購入しているのか、または低価格帯のカテゴリの商品を幅広く購入しているのかを把握することで、顧客のニーズや嗜好に合わせた商品提案やプロモーションが可能となります。
また、RFM-D分析では、顧客の居住地と店舗までの距離を分析に取り入れるため、地理的な要因が顧客の購買行動に与える影響を明らかにし、店舗の立地戦略や、地域に合わせたマーケティング施策の最適化に役立てることができます。
このように、RFMC分析やRFM-D分析を用いることで、顧客の購買行動をより多角的に捉えることが可能となります。
顧客分類ごとのマーケティング戦略
顧客分類と分析によって知見を得たら、それを活かして、効果的なマーケティング戦略を立案・実行することが重要です。ここでは、顧客層ごとのアプローチ方法を紹介します。
優良顧客:維持と育成に努める
優良顧客は、売上やLTVに大きく貢献する重要なセグメントです。
この顧客層に対しては、特別感のある優遇プログラムや、パーソナライズされたサービスを提供することで、ロイヤルティの維持・向上を図りましょう。また、定期的なコミュニケーションを通じて、顧客との関係性を強化することも効果的です。
一般顧客:ロイヤルティ向上を目指す
一般顧客は、優良顧客へと成長する可能性を持つセグメントです。
この顧客層に対しては、購買頻度や金額を増やすためのインセンティブを提供したり、クロスセルやアップセルを促すレコメンデーションを行ったりすることで、ロイヤルティの向上を目指します。
見込み顧客:購買意欲を高めて育成する
見込み顧客は、自社の商品やサービスに興味を示している潜在的な顧客です。
この顧客層に対しては、ニーズに合わせた情報提供や、体験型のプロモーションを通じて、購買意欲を高めていくことが重要です。また、初回購入後のフォローアップを丁寧に行うことで、リピート化を促進しましょう。
潜在顧客:認知度を向上させる
潜在顧客は、自社の商品やサービスを知らない、または必要性を感じていない層です。
この顧客層に対しては、ブランディングや広告活動を通じて認知度を高めていくことが求められます。潜在顧客のニーズや関心事に合わせたコンテンツマーケティングを展開することも効果的です。
顧客分類を活用した事例紹介
事例1:ECサイトでのセグメント別施策
ある大手ECサイトでは、RFM分析を用いて顧客をセグメント化し、それぞれに適した施策を展開しました。
優良顧客に対しては、特別な割引クーポンやイベントへの招待を提供し、一般顧客に対しては、購買履歴に基づいたレコメンデーションを行いました。その結果、優良顧客の購入頻度が向上し、一般顧客の購入単価が上昇するなどの効果が見られました。
事例2:小売店舗でのセグメント別施策
ある小売チェーンでは、顧客の属性と購買行動を分析し、ターゲットとなる顧客セグメントを特定しました。
主要な顧客層であるファミリー世帯に対しては、子ども向けのイベントや、家族で楽しめる商品の品揃えを強化しました。また、店舗までの距離に応じて、近隣の顧客には店舗での特別セールを、遠方の顧客にはオンラインストアでの割引を提供しました。これらの施策により、顧客満足度とロイヤルティの向上に成功しました。
顧客分類の実践ポイント
顧客分類を効果的に実践するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
データ収集と管理をしっかり行う
顧客分類の基盤となるのは、顧客データの収集と管理です。顧客との接点となる様々なチャネル(店舗、ECサイト、アプリ、コールセンターなど)から、顧客の属性や行動に関するデータを収集し、一元的に管理することが重要です。
データ収集に際しては、顧客のプライバシーに配慮し、適切な同意の取得と管理体制の構築が求められます。また、データの品質を維持するために、定期的なクレンジングや更新を行うことも必要です。
分析結果を正しく解釈して活用する
顧客分類や分析の結果をマーケティング戦略に効果的に活かすためには、得られた知見を正しく解釈し、実行が可能な施策に落とし込むことが重要です。
分析結果を解釈する際には、自社の事業特性や市場環境を考慮しながら、顧客セグメントごとの特徴やニーズを読み取ることが求められます。また、分析結果をもとに、優先順位を付けて施策を立案し、PDCAサイクルを回しながら、継続的に改善していくことが大切です。
継続的な改善とアップデートを続ける
顧客の行動や嗜好は常に変化しているため、顧客分類も固定的なものではありません。定期的に分析を行い、セグメントの再定義や、施策の見直しを行うことが重要です。
また、新たな顧客データの収集や、外部環境の変化に合わせて分析手法や活用方法をアップデートしていくことも必要です。顧客理解を深化させ、マーケティング戦略の精度を高めていくためには、継続的な改善とアップデートが欠かせません。
最後に、新規顧客獲得の際には、ぜひ弊社が提供する営業リスト作成ツール「Musubu」もご活用ください。
業界や企業規模、設立年月から現在求人を出している企業まで、細かなセグメントでのリスト作成が可能です。
⇒ 営業リスト作成ツール「Musubu」の詳細をみる
| 監修 | |
|---|---|
 |
Baseconnect株式会社 マーケティングチーム マネージャー 河村 和紀(かわむら かずき) 大手人材紹介会社に新卒入社。その後、Webメディア「ferret」を運営する株式会社ベーシックに入社。営業、営業企画、イベントマーケを経て、マーケティングマネージャーに就任。 主な寄稿実績『マーケター1年目の教科書』、『MarkeZine(マーケジン) vol.66』 |